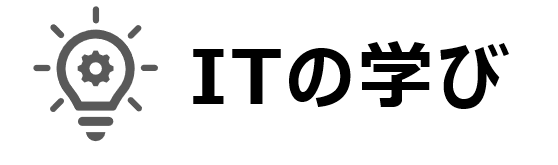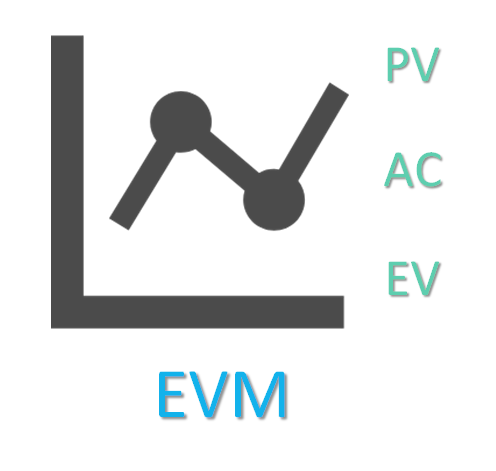突然EVM(アーンド・バリュー・マネジメント)と言われると、何のことか分かりませんが、PMBOK(ピンボック)によるコスト・コントロールとして使われる技法です。
今回はちょっと難しいEVMとその使い方を解説します!
EVMとは?
Earned Value Managementの略で、Earned Valueとは「出来高」のことです。
冒頭にも記載しましたが、プロジェクトマネジメントにおけるコスト・コントロールを行うための技法のことで、次のような目的で使われます。
予算とスケジュールの両方の観点からプロジェクトの遂行を定量的に評価する
三つの基本構成要素を捉えましょう!
EVMにおいては次の三つの基本的構成要素が重要になります!
①PV(Planned Value:計画値)
遂行すべき作業に割り当てられた予算のことです。計画時点で算出することができます。
②AC(Actual Cost:実コスト)
実施した作業のために実際に発生したコストのことです。実測値を用いて算出することができます。
③EV(Earned Value:出来高)
実施した作業の価値です。完了済みの作業に対して当初割り当てられていた予算を算出します。
「達成価値」なんて表現の仕方をするように、達成した「機能数」と、計画段階で求めた「価値(標準工数:工数を機能数で割った値)」を掛け合わせることでEVを算出できます。
予算管理のための四つの値を求めましょう!
EVMにおいては、上記の三つの値を上手に利用して、作業の進捗に問題がないか?費用増になっていないか?などを分析し、対策を打つことができます。
この分析において次の四つの指標値を使います。
①SV(Schedule Variance:スケジュール差異)
「SV=EV-PV」となり、進捗の遅れをコストで表します。SVが「プラス」ならスケジュールは進んでおり「マイナス」なら遅れていることになります。
②CV(Cost Variance:コスト差異)
「CV=EV-AC」となり、コストの超過を表します。CVが「プラス」ならコストは黒字、「マイナス」なら赤字となります。
③SPI(Schedule Performance Index:スケジュール効率指数)
「SPI=EV/PV」となり、進捗状況を指数で表します。SPIが「SPI>1」なら進捗は進んでおり、「SPI<1」なら遅れていることになります。
④CPI(Cost Performance Index:コスト効率指数)
「CPI=EV/AC」となり、コストの効率を指数で表します。CPIが「CPI>1」なら黒字となり、「CPI<1」ならコストが超過していることになります。
更にこれらの値を用いて、完成時の総予算などのプロジェクト完了時の予測ができます。BACやEAC、VACなどありますが、ちょっと深くなっていくのご興味がありましたら最後の参考URLをご参照ください!
まとめ
EVMは指標がいっぱいあり、結構深く違いを理解するのが大変なのですが、今回は浅い部分を簡潔にまとめてみました。
システム開発プロジェクトを行う上でEVMを使って予算とスケジュールを評価することで、失敗しないプロジェクト開発ができるのですね!
以上です!
参考URL)
・PMP試験に出る計算式のまとめ(コスト編):PMP資格取得雑記